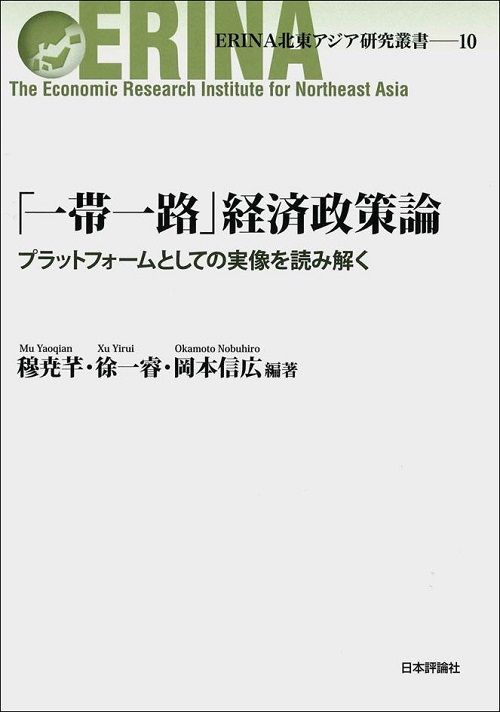
昨日概要だけ紹介した穆尭芊・徐一睿・岡本信広(編著)『「一帯一路」経済政策論 プラットフォームとしての実像を読み解く』(日本評論社、2019年)。我々ロシア地域の関係者は、やはり新井洋史氏による第6章「東北内陸 ―近くて遠い『借港出海』の進展は?」にとりわけ大きな関心を覚える。
「借港出海」とは、海への出口を持たない内陸国が、近隣国の港を利用して海への出口を確保し貿易を行うことを指す。この第6章で具体的に論じられているのは、中国東北部の吉林省および黒龍江省のケースであり、両省の場合は自国の大連港に出るよりもロシアや北朝鮮の港を借りた方が距離的に近いことから、これまでも様々な輸送ルートが検討・開拓されてきた。
問題は、現在も続く両省による借港出海の模索が、今日の一帯一路政策とどのように関係していくかだろう。一帯一路は、一般的には、中国と欧州を結ぶものとイメージされることが多く、中国東北地方から東に向かう借港出海はそれにはマッチしないのではないかという疑問も湧く。しかし、実際には吉林省および黒龍江省は、以前からの借港出海の試みを、今日では一帯一路の名の下で推進するしたたかさを見せているということである。第6章の締めくくりでは、以下のように論じられており、なるほどと納得させられた。
歴史的な出自が異なり、一見無関係に見える政策を、黒龍江省や吉林省はいとも簡単に「一帯一路」に結び付け、しかも停滞気味だった状況を打破する契機として活用している。政策主体の工夫次第で、いかなる政策であっても「飲み込む」ことができる「一帯一路」の懐の深さを示す好事例である。
ブログランキングに参加しています
1日1回クリックをお願いします

